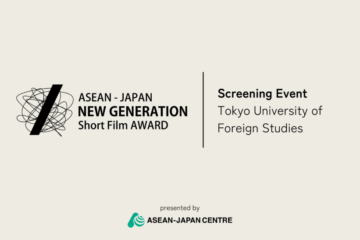※以下の記事には、受賞作品の内容に関するネタバレが含まれています。記事を読む前に作品をご覧になりたい方は、当センターのYouTubeチャンネルにて公開しておりますので、以下のリンクよりご視聴ください。
プレイリスト:
https://www.youtube.com/watch?v=cgA77AiGd1M&list=PLEeibcySrqF9ol1okUNoixP5NLZjEyo5G
(各作品の上映時間は、クレジットを除き2〜3分です。)
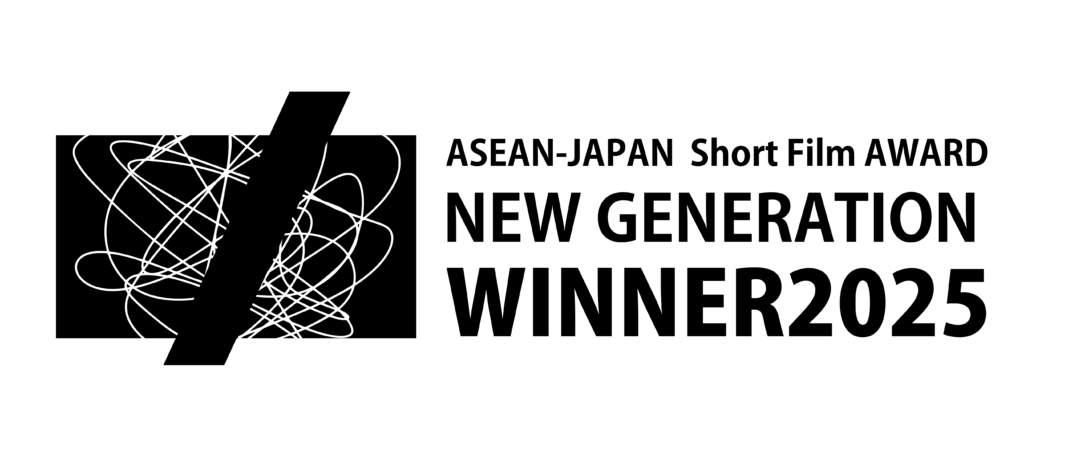
昨年、日本アセアンセンターは「2025 ASEAN-Japan NEW GENERATION ショートフィルム・アワード」を開催しました。2025年のASEANテーマに着想を得て、若手映像クリエイターたちには「I Belong(私の居場所)」をテーマにした2〜3分のショートフィルムを制作。ASEAN全10カ国(募集当時)から150作品を超える応募があり、その中から最終的に5作品が受賞の栄冠に輝きました。
本記事では、受賞作品を手がけた監督たちを紹介し、彼らのストーリーや作品に込めた想いについてお届けします。
『PROM QUEER』 – ディラン・セリオ(フィリピン)
2025年の「Most Popular Film Award(観客賞)」を受賞したのは、ディラン・セリオ監督の『PROM QUEER』です。現在20歳のディランさんは、フィリピンでエンターテインメント・マルチメディア・コンピューティングを専攻する学生です。
以前から映像制作に関心を持っていたものの、本格的に活動を始めたのは大学に入学した2年前のことでした。インタビューの中でディランさんは、「Alamat ng SAGA」という映画制作団体に出会ったことがきっかけで、脚本家としてこの道に足を踏み入れたと語っています。今では映像作家として活躍するディランさんが今回のアワードに参加した理由は、LGBTQに関するメッセージをフィリピン国内だけでなく、日本を含む海外の人々にも届けたいと考えたからでした。
「多くの人が、拒絶されたり批判されたりすることを恐れて、本当の自分を隠していると思います。この映画では、自分らしくあることの難しさを描くと同時に、愛する人たちに受け入れられたときに得られる解放感も表現しました。自分らしく生きることが難しい社会であっても、他者からの受容や『自分の居場所』を見つけることは可能なのです。」

『PROM QUEER』は、主人公のレックスがプロム(卒業ダンスパーティー)に着ていく衣装に悩み、最終的にある意外な服装を選ぶまでの物語です。映画は、晴れ舞台に向けて準備を進めるレックスと友人たちの感情に焦点を当てています。ディラン監督は、緻密なサウンドデザインや力強い演技、そして明確なビジョンを通じて、友人たちの屈託のない高揚感と、レックスが抱える内面的な葛藤を見事に対比させています。『PROM QUEER』は、こうした葛藤の多くが、身近な人々の反応に対する不安ゆえに、誰にも見えない「閉ざされた扉の向こう側」で起きているという現実を描き出しています。

物語の結末には、ディラン監督の「たとえ社会が保守的であっても、人々は多様なアイデンティティを受け入れ、理解し始めている」という希望に満ちたメッセージが込められています。監督は、他の国々も同じような変化の過程にあり、これは国境を越えて共感し合える経験だと信じています。

『Be Here, Again』 – ニコル&アナベル(インドネシア/シンガポール)
内省的な作品『Be Here, Again』を手がけたのは、23歳のニコル・サントソさんと20歳のアナベルさんです。二人は脚本、演技、撮影、編集のすべてを自分たちだけで行い、このショートフィルムを完成させました。

本作は、新しい環境で自分の居場所を見つけようとする二人の友人の、飾らない交流を描いています。シンガポールの象徴的な場所を捉えた独創的なカメラワークと、心温まる会話が組み合わさり、観る人を魅了する励ましの物語となっています。当初はシンガポールの多様な料理や場所を紹介する映画になる予定でしたが、制作が進むにつれ、その国と、そこで生きる「人間」との繋がりに焦点が移っていきました。
驚くべきことに、ニコルさんとアナベルさんのクリエイティブな方向性は全く異なります。ニコルさんは象徴的な表現を多用するスリラーや心理ドラマを好む一方、アナベルさんはドラマやアクションを抑えた「日常系(スライス・オブ・ライフ)」の物語を好みます。『Be Here, Again』は、この相反するスタイルを丁寧な映画作りによって融合させ、張り詰めた緊張感と心地よい温かさという、独自のバランスを生み出すことに成功しました。
「見逃してしまいそうなポイント」について二人に尋ねると、序盤のシーンを挙げました。主人公(ニコルさんが演じる)がシンガポールの観光地を散策している際、人混みに出くわしてその場から逃げ出す場面です。一見何気ないシーンですが、これは後半で描かれる主人公の不安を予兆する伏線となっています。二人はこのシーンを通じて、「孤独や恐怖は、時として自分自身の考え方や行動によって引き起こされることがある」ということを表現しようとしました。

インドネシアからシンガポールへ移住した経験を持つ二人は、シンガポールの多文化的な環境と、慣れ親しんだ場所を離れる際の心情を映像に収めたいと考えました。ASEANや日本の観客に向けた彼女たちのメッセージは、「変化を受け入れ、その土地独自の文化や多様性を尊重し、自分自身の恐れを理解することこそが、自己成長と新たな繋がりへの一番の近道かもしれない」というものです。

『HE WHO HAS NO NAME』 – エドセル・ガスメン(フィリピン)
もう一人の若き才能は、ショートフィルム『HE WHO HAS NO NAME』の監督であり、フリーランスの写真家としても活動する23歳のエドセル・ガスメンさんです。写真家として活動を始めたエドセルさんは、数々の映画に影響を受けて映像制作に興味を持ち、2023年から本格的に映画作りをスタートさせました。

エドセル監督は冒頭から、緊張感漂う慌ただしい試験会場へと観客を引き込みます。教室中に鉛筆を走らせる音が響く中、一人の生徒だけが「自分の名前を書く」という行為に苦戦しています。物語は最初から最後まで観客の好奇心を刺激し続け、最後にようやくその真のメッセージが明かされる構成になっています。インタビューでエドセルさんは、観客を最後まで飽きさせないために、こうした比喩的なストーリーテリングの手法を好んで用いると語っています。また、主演俳優二人の説得力ある演技も、作品のトーンを決定づける重要な要素となりました。

実はこの作品は、もともとフィリピンの出生登録局が主催した、出生届の提出を啓発するためのコンペティション向けに制作されたものでした。アイデアを練る中で、エドセルさんは学生時代にテストで名前を書き忘れ、成績がもらえなかった経験を思い出したそうです。このエピソードが、本作のベースとなりました。エドセル監督は、この作品を通じてASEANや日本の人々に「アイデンティティや居場所の重要性、そして誰もが『認知される権利』を持っていること」を感じ取ってもらいたいと願っています。

『Saudade』 – タハニ・ヴィドラ・プトリ(インドネシア)
インドネシアからは、24歳のタハニ・ヴィドラ・プトリさんの作品も選ばれました。彼女の代表作『Saudade』は、ある子供が「音」を通して過去を回想する物語です。

タハニさんは物心ついた頃から創作活動に親しみ、小学生の頃から物語や詩を書いていました。当初は脚本家を目指していましたが、映像制作の道に進んだのは偶然が重なった結果でした。学校の映画部で活動していたある日、カメラマンが急病で倒れてしまったのです。代役としてカメラを握ったタハニさんは、そこで映画に対する全く新しい視点を得ました。言葉や文章だけでなく、映像や音を通して物語を構想するようになったのです。それ以来、彼女は2017年からコンスタントにショートフィルムを作り続けています。
普段は15〜30分程度の作品を手がけることが多いというタハニさん。「シンプルで分かりやすいけれど、独創的で力強い物語」を好みます。今回のテーマ「I Belong」を聞いてすぐに思い浮かんだのは、有名な観光地ではなく、人々がそれぞれの記憶や瞬間を刻んだ「思い出深い場所」でした。また彼女は、このアワードを、母国インドネシアと彼女が所属する映画コミュニティ「Drama Anak Bintan」の名を広い世界に知ってもらうチャンスだと捉えました。タハニさんはこの作品を通じて、「何気ない場所であっても、誰かにとってはかけがえのない記憶になり得る」ということを伝えたいと語ります。『Saudade』では、視覚や触覚といった一般的な感覚ではなく、「音」と「感情」を通じて記憶が探求されます。主人公のナラは、その音を通じて、自分のコミュニティや文化、そして家族との繋がりを取り戻していくのです。

注目してほしい点として、タハニさんは冒頭の色彩について触れました。視力を失ったナラの視点を表現するために、あえて色味を抑えたトーンを使用しています。しかし、ラストシーンでは色彩が戻り、「傷ついた心もいつか癒えること」、そして「どんなに暗い時でも、愛が光をもたらしてくれること」を象徴的に描いています。ASEANや日本へのメッセージとして、タハニさんはインドネシアの「別の側面」を共有したいと語りました。あえて豊かな自然や伝統文化を前面に出すのではなく、インドネシアの人々が持つ温かさや共感力、そして喪失の中でさえ希望や愛を見出す「強さ」を描きたかったのです。

『The Perfect Employee』 – グエン・ナン・ハイ・アン(ベトナム)
ベトナム出身の20歳、グエン・ナン・ハイ・アンは、現在、南カリフォルニア大学で映画・テレビ制作を学んでいます。アンさんの創作の原点は音楽でしたが、そこからショートフィルムへと表現の幅を広げました。実は、映像制作を始めた当初の目的は、自分の曲のミュージックビデオを作ることでした。しかし、理想通りのビデオを作ってくれる人が見つからなかったため、アンさんは自分で作ることを決意しました。そこからカメラに慣れ親しんでいくうちに、いつしか映画制作そのものを志すようになったといいます。
『The Perfect Employee』に登場するのは、一見すると同僚や上司から好かれているように見える、ベトナムのある会社員です。しかし物語が進むにつれ、彼が同僚と関わるのは仕事の時だけで、オフィス内の社会的な交流の輪には入っていないことが明らかになっていきます。

この作品の着想は、一生懸命努力して就職したにもかかわらず、後になって「仕事が楽しくない」と気づいた友人たちを見て得たものでした。これに触発されたアンさんは、テーマに対して一味違うアプローチを試みました。「仕事の成果だけは評価されているが、その環境には明らかに馴染めていない(Belongしていない)」キャラクターを描くことにしたのです。

アンさんはこの映画を通じて、多くの人が1週間の大半をオフィスで過ごしているにもかかわらず、職場に「自分の居場所」を感じられていないという現実を伝えたかったと語ります。そして、たとえ今の環境が楽しいものでなくても、そうした経験こそが、本当に自分が属するべき場所を見つけ、感謝するためのきっかけになるのだと気づいてほしいと願っています。
撮影は貸しオフィスで行われました。周囲で他の人々が実際に働いている環境での撮影は、キャストにとってリアルな演技を引き出す助けとなり、同時にセットを作り込む手間を大幅に省くことにもつながりました。自身の映像スタイルについて尋ねると、アンさんは「まだ模索中」だと答えました。ただ、『The Perfect Employee』のスタイルは、自分が最終的に目指す方向性にかなり近いかもしれないとも語っています。ASEANや日本の人々に対し、アンさんはこうメッセージを送ります。「言葉や文化、環境は違っても、私たちが抱く感情や経験は似ています。どこにいても、私たちは互いに共感し合うことができるのです。」

おわりに
ASEAN諸国の若者の間では映画を含む動画コンテンツを制作する動きが急速に広まっています。こうした作品を通じて、伝統と現代の両方を知るASEANの若い世代ならではの新鮮なレンズを通し、新しいテーマも普遍的なテーマも探求されていくことでしょう。日本アセアンセンターは、こうした映画を日本の若い観客に届けることで、ASEAN諸国と日本の人々の間に深い理解と共感を育みたいと考えています。背景は違っても、それぞれの物語の根底にある感情、希望、そして葛藤は、私たち全員に共通するものではないでしょうか。