記録映像はこちらからご覧いただけます。
発表資料はこちらからダウンロードいただけます。
2025年7月31日、日本アセアンセンターは、OECD東京センターおよび東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA)との共催により、「日本・アセアンにおける『信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)』推進に関するセミナー:政策・実践・パートナーシップ」を、東京の日本アセアンセンター・アセアンホールおよびオンライン会議システムを通じて開催しました。本セミナーでは、信頼性が高く相互運用可能な国境を越えるデータ流通が、地域における革新、貿易、そして持続可能な成長をいかに支えるかについて、活発な議論が行われました。
開会挨拶
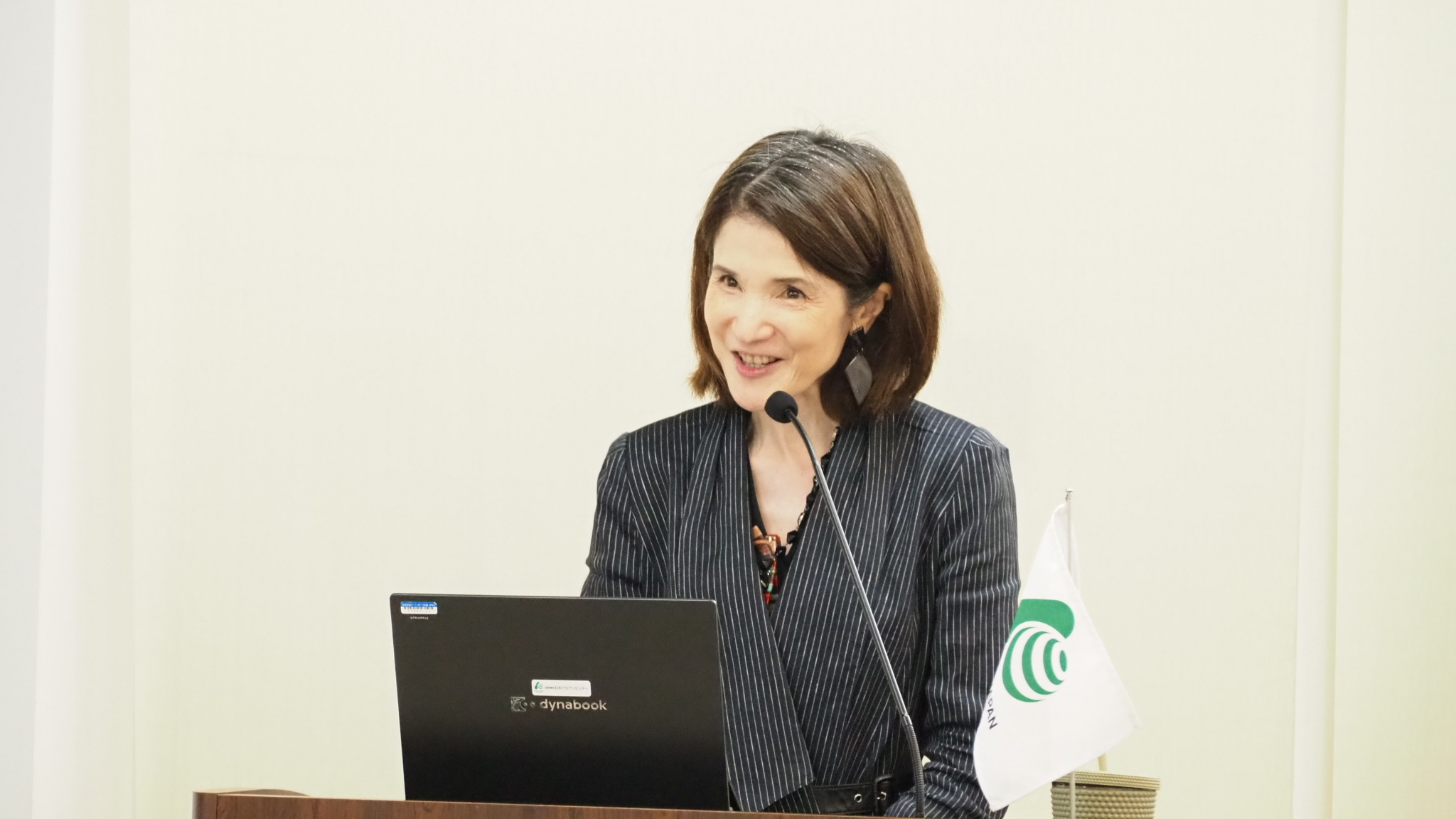
OECD東京センター所長の上田直子氏は、参加者を歓迎し、DFFTの理念が日本の2019年G20議長国としての提唱に端を発し、その後、世界的なデジタル分野の統治における中核原則へと発展してきた経緯を強調しました。さらに、個人情報保護、サイバーセキュリティ、人権尊重を基盤とする、安全かつ途切れのないデータ流通こそが、データ駆動型経済の潜在力を最大限に引き出すために不可欠であると述べました。
第1セッション:政策から実践へアジアにおけるDFFTの具体化
司会: 久保田 有香日本アセアンセンター 事務総長補佐)
登壇者:
Speakers:
- 舟橋 卓也 氏(内閣官房 デジタル行財政改革実行本部事務局 参事官補佐)
- 森川 純 氏(経済産業省 通商政策局 通商交渉官付 デジタル貿易政策室長)
- 目黒 麻生子 氏(OECD 科学技術革新局 データ流通・統治・プライバシー課 DFFT主管・上級政策分析官)
- ディアン・ウーランダリ 氏(アセアン事務局 アセアンICTセンター副所長)

第1セッションでは、DFFTをいかに政策の枠組みや制度的な協力関係へと具体化しているかについて議論が行われました。舟橋氏は、2026年までに官民連携によるデータ共有モデルの試行を行い、個人情報保護法を補完する新たな法案を提案することを盛り込んだ「データ活用戦略」を紹介しました。続いて森川氏は、日本の三本柱からなるデジタル貿易戦略について説明しました。すなわち、DFFTを環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)、地域的な包括的経済連携(RCEP)、および二国間協定に組み込むこと、世界貿易機関(WTO)の電子商取引共同声明イニシアティブ(電子送信に対する関税免除のモラトリアムを含む)の議長を務めること、そしてOECDの調査成果を活用してデータローカライゼーション(域内保存義務)の障壁を撤廃することです。
目黒氏は、新たな官民連携枠組みである「パートナーシップのための制度的アレンジメント(IAP)」を紹介しました。これは、デジタル決済からプライバシー保護技術に至るまでのプロジェクトを実施し、その成果をOECDの正式な意思決定に反映させる官民共同のプラットフォームです。ウーランダリ氏は、アセアンの三本柱からなるデータ統治の枠組み、中小企業向けモデル契約条項、そして2022年のインドネシアG20議長国経験から得られた「適法性、公平性、透明性」の組み込みに関する教訓を紹介しました。
パネル討議では、各省庁間の規制調整、関係者間の継続的な対話、そして具体的な試行事業こそが、信頼の構築、法的な空白の解消、そして途切れのない国境を越えるデータ流通の基盤整備に不可欠であることが強調されました。
第2セッション:技術と統治における信頼構築の障壁の把握
司会:上田直子氏(OECD東京センター 所長)
登壇者:
- 石井 純一 氏(デジタル庁 国際データ戦略・国際担当 国際データ戦略統括官)
- アイビー・グレース・ヴィラソト 氏(フィリピン 国家プライバシー委員会 政策開発課 課長 兼 法務官)
- ラリッサ・リム 氏(シンガポール 情報通信メディア開発庁 国際関係・政策戦略部 エグゼクティブマネージャー)
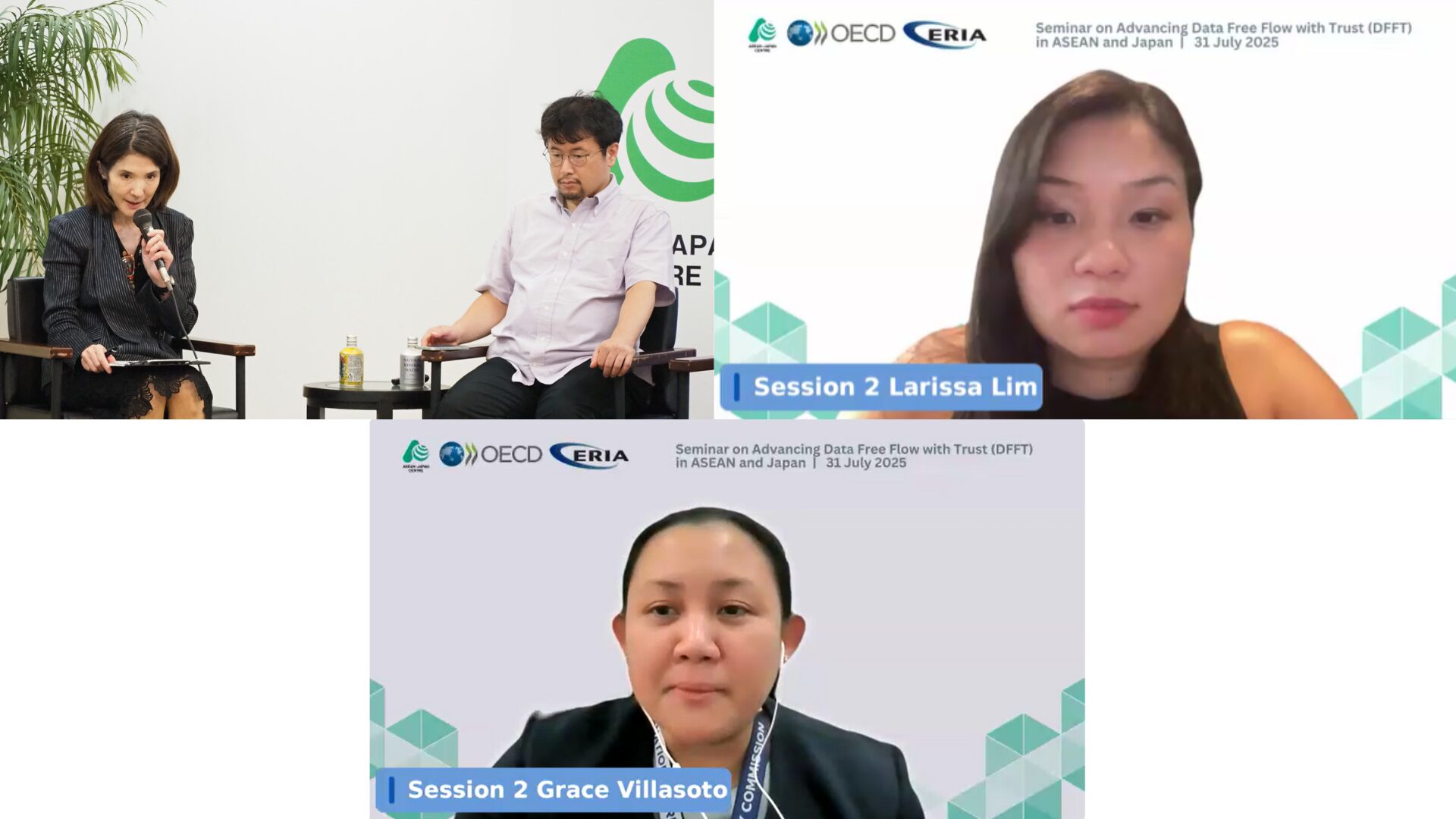
第2セッションでは、現実的な課題と日アセアンの協力に焦点が当てられました。石井氏は、法解釈の集約とAIによる質疑応答ツールの提供、さらにプライバシー保護技術の試行事業を目的とした「アセアン・データガバナンス・ハブ」の立ち上げ計画を紹介しました。ヴィラソト氏は、国内における信頼の構築には、国民への広報啓発活動、データ保護責任者(DPO)の能力強化、そして新興技術への対応を含む法執行力の強化に向けた立法改革が不可欠であると強調しました。
リム氏は、法定基準として制度化された国家レベルの「データ保護トラストマーク」および、プライバシー保護技術(PETs)やAI保証のためのイノベーション・サンドボックスを紹介しました。3回にわたる質疑応答を通じて、パネリストらは、規制の透明性、共通の技術基準、そして地域全体での能力強化ワークショップが信頼の格差を埋めるために極めて重要であるとの認識で一致しました。
第3セッション:革新の促進 DFFTの分野別応用と事例研究
司会:カトリナ・ナバロ氏(日本・アセアンセンター 調査・政策提言部 プログラムマネージャー)
登壇者:
- 猪飼 祐司 氏(経済産業省 企業行動課 国際室・デジタル戦略室 室長)
- 中山 大介 氏(東アジア・アセアン経済研究センター デジタル革新・持続可能な経済担当 チーフマネージャー)
- 藤田 孝典 氏(公益財団法人 東京財団政策研究所 上席研究員)

第3セッションでは、DFFTがいかに具体的な試行事業へと展開されているかが紹介されました。猪飼氏は、自動車用バッテリー分野で試行されている安全なデータ共有基盤「ウラノス・エコシステム」を紹介しました。これは、EUのカーボン報告要件への対応やリアルタイムでのトレーサビリティ確保を可能にするものです。 中山氏は、部品単位でのサプライチェーンのトレーサビリティを実現する概念実証を説明しました。これは、出発地から目的地までの所在地情報や在庫情報を取得し、強靭性と効率性の向上を図るものです。 藤田氏は、日本の「医療分野デジタル変革」構想を紹介しました。健康保険証と国民IDの一体化、診療報酬手続きの近代化、そしてケアの質向上と国際的な研究連携を支える「インフォームド・コンセント2.0」の導入を柱としています。
パネル討議では、事例に基づく試行事業、共有された信頼の枠組み、そして感染症対応や個別化医療に資する共同の医療分野「手引き」の重要性が強調されました。
閉会挨拶

日本アセアンセンター事務総長の平林国彦氏は、全ての登壇者および参加者に謝意を表しました。さらに、信頼性のあるデータ流通は「デジタル経済における真の通貨」であると強調し、各国政府、産業界、多国間機関に対し、規制改革、官民連携、そして包摂的な試行事業を通じて、この取り組みの勢いを持続させるよう呼びかけました。



